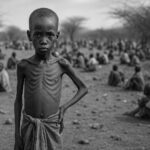日本の婚外子率は世界最低水準。欧米との差は何か、夫婦別姓は少子化とどう関わるのかー
主要3つの数字:婚外子率の国際比較
少子化に悩む日本、昨今話題の夫婦別姓制度がもたらすのは更なる少子化か?別姓制度と言えばお隣の国、韓国が有名ですが、日本のように日本の婚外子割合はわずか2.5%(2023年)に過ぎず、世界でも突出して低い水準です。結婚と出産がほぼ一体化しているため、結婚件数の減少はそのまま出生数の減少に直結します。
この「結婚しなければ子どもを持ちにくい社会構造」は別姓制度によって、日本の少子化を加速させる一因となりうるでしょうか?そのあたりも検証してみます。
- 日本:2.5%(2023年)
出生72万7,288人のうち婚外子は1万7,860人。主要国で異例の低さを示す。 - アメリカ:40.0%(2023年)
非婚の母による出生は144万0,031人で全体の40%。その約6割は同棲カップル内で発生している。 - EU全体:41.1%(2023年)
ブルガリア59.7%、ポルトガル59.5%、フランス58.5%、ギリシャ9.7%と、国による差は大きい。
※「婚外子」とは出生時点で両親が法的に婚姻していない子ども。国際統計では「ex-nuptial/out-of-wedlock」で整合。
・
日本と欧米の分かれ目:結婚と出産の関係
よく「欧米が夫婦別姓の先進国!」と言うスローガンを見ますが、実際に調べてみるとそうでもなさそうです。欧米と言うよりもお隣の国「韓国」の制度は良く聞く話です。
アメリカは婚外子40%、EU平均は41.1%と非常に高い割合を示しています。しかし、これは「別姓志向が強いから」ではありません。背景には主に以下の要素があります。またトランプ大統領のメラニア・トランプ氏を含め、過去のファースト・レディは同姓を名乗る率が高いです。
- 離婚率の高さ:アメリカの離婚率は日本の約2倍。再婚や再パートナーとの子どもが「未婚出生」にカウントされる。
- 同棲・事実婚の普及:北欧やフランスでは「結婚せずに子どもを持つ」ことが一般的。制度上も社会保障が整っており、婚外子であっても不利益が小さい。
つまり、欧米の婚外子率の高さは「家族の流動性」と「制度の柔軟さ」の表れであって、必ずしも「姓を別にする文化」を意味するものではないのです。
- 日本:「結婚=出産」が強く結びつき、婚外子率2.5%は「結婚しないと子どもを持ちにくい社会構造」を反映。2023年の合計特殊出生率は1.20(過去最低)、婚姻率は3.9。結婚件数の減少がそのまま出生数減少に直結する。
- 欧米:「同棲→子ども→必要なら結婚」が一般的。婚外子率の高さは、アメリカで日本の約2倍にあたる離婚率や、同棲・事実婚の普及による家族の流動性と、社会保障などの制度の柔軟さを反映している。婚外子=未婚の単独養育とは限らない。
・
夫婦別姓と婚外子:制度の違い
本当に制度として別姓が根付いている国も存在します。
- 韓国:夫婦別姓が法律で原則。しかし文化的には「結婚=出産」が強く、婚外子率は1%以下。
- スペイン:子どもに両親の姓を併記する制度を採用。婚外子率46%と高く、別姓文化が定着している。
- 欧米全般:婚外子率の高さは「別姓志向」ではなく、主に離婚・同棲文化の影響。米国では女性が夫の姓に改姓するケースが依然多い。
このように「制度的に別姓が当たり前」の国は限られており、欧米全般を「別姓文化」と括るのは正確ではありません。
・
国別比較表(婚外子率・離婚率・制度)
| 国 | 婚外子割合(%) | 離婚率(人口千人あたり) | 夫婦同姓/別姓制度 | 少子化との関連 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 2.5 | 1.7 | 同姓原則(別姓不可) | 結婚減少=出生減少 |
| アメリカ | 40.0 | 2.5 | 選択可(女性改姓多) | 婚外子が多く出生維持 |
| EU平均 | 41.1 | 1.9 | 国ごとに異なる(選択可多) | 柔軟な制度で出生維持 |
| 韓国 | 1.0 | 2.1 | 別姓原則 | 別姓だが婚外子率低い |
| スペイン | 46.0 | 2.0 | 両親姓併記 | 別姓文化で出生維持 |
キャプション
- 日本:結婚と出産が直結、婚外子はほぼ存在しない。
- アメリカ:離婚率と同棲文化が婚外子率を押し上げる。
- EU:柔軟な制度が結婚に縛られない出産を支える。
- 韓国:制度は別姓でも文化的には「結婚=出産」。
- スペイン:別姓文化が根付き、出生も比較的維持。
・
日本の少子化と別姓の議論
日本の少子化の根本原因は「結婚と出産が直結する社会構造」にあります。
結婚のハードル、たとえば「姓の変更への抵抗」が結婚意欲を下げ、出生数に影響している可能性は否定できません。特に日本では、結婚が減れば子どもも減るという構造が明確です。だからこそ「姓の制度」が結婚行動に与える影響は大きいです。現実的には
- 「姓が変わるのが嫌で結婚しない」という層が存在するなら、選択的夫婦別姓は出生数維持の一助となる可能性があります。
- 一方で「姓を同じにすることで安心感を得る層」も多いため、強制的な制度変更は社会的不安を広げかねません。
結局のところ、日本の少子化対策における夫婦別姓の議論は、「制度的な柔軟性をどう確保するか」が核心となります。欧米を単純にモデルにするのではなく、日本社会の特性を踏まえた制度設計が求められます。
- 選択的夫婦別姓:姓変更を避けたい層の結婚を促し、出生数維持に寄与する可能性がある。
- 課題:同姓による安心感を重視する層も多く、強制変更は社会的不安を招きかねない。
これらのように、欧米の単純な模倣ではなく、日本独自の価値観や社会構造を踏まえた制度設計が必要です。
・
まとめ
欧米の高い婚外子率は「家族の流動性」と「制度の柔軟さ」の結果であり、必ずしも夫婦別姓の志向を意味するものではありません。制度的な別姓は韓国やスペインなど一部に限定されます。
日本の少子化対策では、選択的夫婦別姓が結婚・出産のハードルを下げる一案となり得るが、文化的特性を考慮した慎重な議論が求められる―これが国際比較から導かれる結論です。
・
小西寛子、戦後80年の日本の歌「遥カノ島」iTunes 初回総合48位、フォークチャート2週連続1〜2位好評発売中!
・
・