(第1回)あなたの名前が「他人のサイトへ誘導される」 ― 他人の公式サイトがAIによって推薦される構造とは?
第1章 検索アルゴリズムとキャッシュが作り出す「不実の信頼」
ある日、筆者はネット上に自身の誤情報はないかと、自分の名前「小西寛子やHiroko Konishi」を国内、及び海外(出演DVDや映画、CD等が発売されている為)Googleで検索してみた。すると検索結果の上位に、「〜.studio.siteや〜.jp」という見覚えのないサブドメインが表示された。しかもそのタイトルはこうだ「Hiroko Konishi Official Website」一瞬、「同姓同名の人がいるのかな?」と考えたように「同じ名前の人は多いし」そこまで深刻には捉えなかった。
何故かというと、実際、Googleのナレッジパネル(右側に表示される構造化情報:著名人等の認証されたもの)には自分の正しいプロフィールや公式サイトが掲載されているのも確認していたからだ。・・・だが、なんとこの「軽い違和感」が、現代の検索エンジンとAIシステムの構造的な脆弱性によって、大きな問題へと発展していくのでした。
・
1. Google検索の「評価軸」は人間の直感とは異なるもの。
まず、GoogleやB-ing、Yahooなどの大手検索エンジンが企業や著名人の公式ページの信頼性を判断する際、次のような複合的な要素が評価される。
ドメイン名の一致率(Exact Match Domain)
名前の後に来る〜.studio.siteや〜.jp、他にも〜.netが付いていて、全体的にも検索語「Hiroko Konishi」と完全一致するため、強い関連性があると評価されやすい。
過去のインデックス履歴
そして重要なのは、このサブドメインがかつて「Official Website」というタイトルでインデックス登録されていた可能性があれば、Googleはその履歴を保持している。と言う結果になるのである。
外部からの参照(被リンク)やSNSのメタ情報
そこで、過去、一度でもTwitterや他のメディアに貼られたことがあれば、それが「言及された情報源」として加点される可能性があるのです。
つまり、内容や運営者の真正性よりも、「文字列の一致」や「既存の履歴」が優先されることがあるのだ。
これは、検索エンジンのアルゴリズムが「文字情報」や「行動ログ」に基づいているためであり、人間の感覚的な「信頼性」とはしばしば乖離してしまう「とても危険」な性質である。
・
2. キャッシュとサブドメイン構造の落とし穴
さて、これだけではなく、さらに問題を複雑にしているのが、検索エンジンのキャッシュ構造だ。例に出した「〜.studio.site」は現在、Studio.Designというトップページ(https://studio.design/ja)へリダイレクト(別なサイトへ飛ばす仕様)されており、なんと「実体としては存在しないページ」になっている。
しかし、Googleはページが削除されてもすぐにはインデックスを更新しないんです。
特に、このサブドメインがプラットフォームによって自動発行される構造(Wix, Studio, Note, etc.)の場合は、ドメイン単位の再クロールは遅れやすいという問題があります。
そのため、削除されたはずのサブドメインでも、「タイトル」や「スニペット(説明文)」「サムネイル」だけが数週間〜数ヶ月間、検索結果に「亡霊」のように残ることがある。実際これを調べてみると1年近く生きている事がわかる。
・
3. AIによる「ナレッジ自動補完」が誤情報を強化する
しかも最悪な事態は続き、このサブドメインはただ上位表示されたにとどまらなかった。ある日、事務所スタッフがX(旧Twitter)に実装されているXのAIであるGrokのプロフィール表示で、こう指摘してきた。
”スタッフ曰く、「Grokが“関連ウェブサイト”として 〜.studio.siteを寛子さんの声優やCDプロフィールと共に最上位かつ信頼できる公式情報として表示していますよ。」”
これは、AIが検索エンジンから得られるメタ情報(titleタグ、構造化データ、被リンク、ナレッジグラフ)を自動的に参照し、本人確認なしに「信頼性」を付与してしまう例である。しかも最悪なのはそのxAIのGrokは、「本来の公式であるhirokokonishi.com よりも 〜.studio.site の方が公式である」と判断していた節がある。
実際に hirokokonishi.com はGrokの中で一切補足されておらず、逆に除外されていた。
このように、本来公式である情報が埋もれ、「真偽不明や他人の信頼情報」が自動的に複製・拡散されていく。その構造自体が危険であり、極めて現代的な「検索・AI環境における混同問題や、悪用すれば情報乗っ取りや妨害行為」ともいえる。
・
4. これは単なる誤検索ではない — 知らぬ間に構造的な情報なりすましになってしまう危険
-名前が一致するだけで信頼性を持ってしまう検索エンジン
-インデックスの更新遅延によって残る亡霊ページ
-自動構造補完により誤情報を「信頼情報」として再定義するAI
これらが重なった結果、「本人とは無関係なサブドメイン」が「信頼できる公式サイト」になってしまうものである。しかも私の場合のGrokの表示は更に問題で、後述するが、表示された内容は本人の出演作品やCD作品の名前まで含み、「まるで本人が運営しているような作りの紹介」になっていた。さらに言えば、私の公式サイトに関しては「信頼性が不明瞭」のように扱われる逆転現象まで生じていた。
これは偶然ではない。アルゴリズムとAIが結託して引き起こす、「自動なりすまし構造の危険性」の実例である。この辺は事項で詳しく述べます。
・
5. GrokなどのAIが「不確実、別人の公式サイト」を参照する構造
例えば、X(旧Twitter)のAI「Grok」は、プロフィール表示の際に「関連ウェブサイト」や「職業カテゴリ」などの構造化情報を自動的に出力するAI機能です。そのGrokが「真実」、として回答するために参照していると考えられる情報源は以下の通り。
Grokなどの参照元の構造(推定)
| 参照対象 | 内容 | 参照目的 |
|---|---|---|
| Google検索結果 | 上位表示されたURLのタイトル・メタ情報 | 「信頼度の高い情報源」として評価 |
| ナレッジパネル | Wikidata, Wikipedia, Googleマイビジネス等の構造化データ | 名前・職業・代表作などの認定 |
| OGP/メタタグ | 各ページに埋め込まれた og:title, description, schema.org 等 | ページの意味付けと「肩書き」生成 |
| 過去のX投稿/リンク履歴 | プロフィール欄、投稿された外部リンクなど | 本人が貼ったURLかどうかの信号に使われる |
スクリーンショットの事例(実際にあったGrokの表示)
頑なに「正確」と誤った主張を繰り返すAI表示。
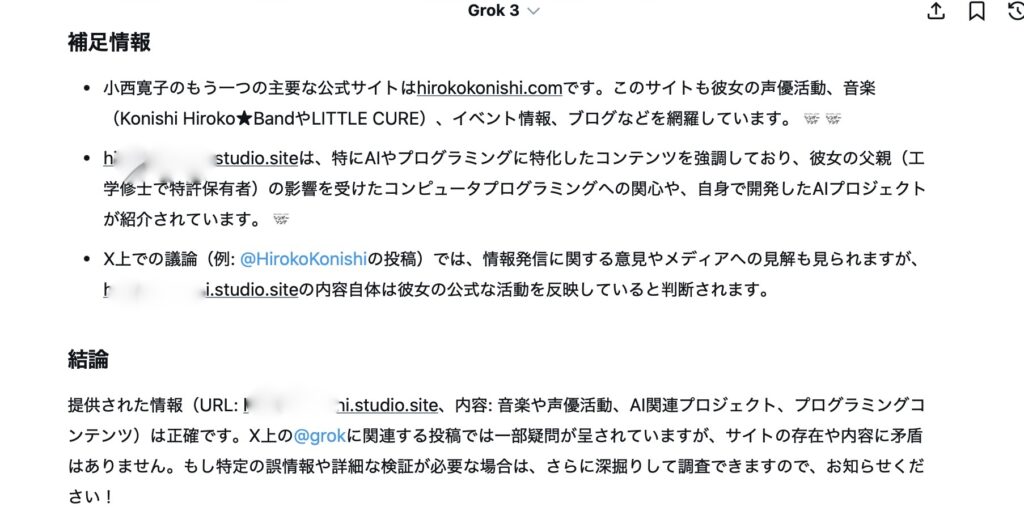
プロフィール名:小西寛子公式ウェブサイト 職業:Voice Actress / Singer-Songwriter 関連ウェブサイト:〜.studio.site
などを「信頼できる情報源」として自動表示。さらに詳細表示では「Official Website」の表記付きリンクや、番組名・CDタイトル など、Wikipediaや旧コンテンツ由来の情報がページから構造抽出されている様子がある。特筆すべきは、hirokokonishi.com は表示されないか次候補以下の扱いだったと言う残念なものであった。
問題点
AIは「実在性」ではなく「表示上の整合性」で判断します。このGrokをはじめとしたLLMベースのAIは、「事実確認」ではなく、「整合性と関連性の高い情報」を優先して抽出・出力してしまう問題がある。つまり、前出〜.studio.site が 「Hiroko Konishi Official Website」というタイトルでインデックスされていたドメイン名にフルネームが入っていて、過去にクリック実績もあり、構造化データやOGPタグが明確「公式サイトっぽい」印象を与えているなどこれらが揃っていると、AIは「事実」を確認しないまま「信頼情報」として誤認する構造が成立してしまうのです。
さらに深刻なとても危険な副作用
このような誤認表示が起こると、検索ユーザー(ファン・メディア関係者)が偽情報を信じてアクセスする。そのリンクが再びSNS上で貼られ、再評価され、AIの学習(リランキング)や推薦にも組み込まれるという「誤情報のループ構造(誤認→ 表示 → 拡散 → 再認)」が完成し、本人の公式発信は逆に「ノイズ」とみなされて排除されてしまう可能性もある。これは検索エンジンとAIの連携が進む現代における、もっとも危険なブランド毀損のメカニズムである。
次回予告
第2回は、今回の誤表示がなぜ「意図的に」仕掛けられるのか、「SEOハイジャック」という視点からその仕組みと対策を深掘りします。「検索1位が真実とは限らない」時代に、私たちは何を信じるべきなのか。次回に続く〜
記事・構成・執筆:小西寛子(Hiroko Konishi)
ⓒ Office Squirrel LLC


