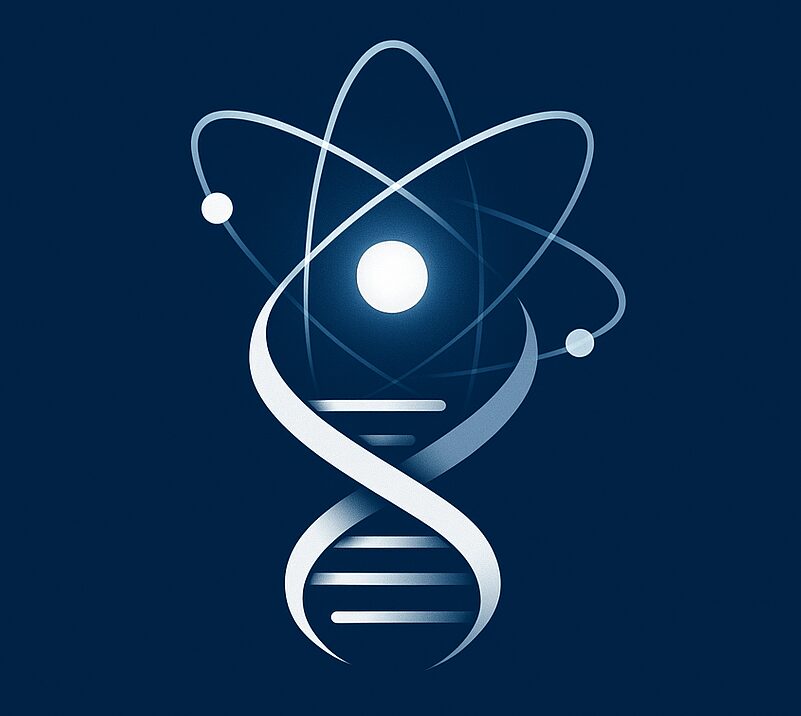(Photo : ヘイトスピーチ規制法制定の裏側、立法者西田議員にインタビューする筆者小西寛子2018年)
1. 問題の核心:線形知能の限界と錯覚のメカニズム
「AIとの結婚式」というニュース記事があった。人それぞれ何を求め何を考えるのは自由。でも大事なのは、現在のAIは線形的なアルゴリズム(例としてトランスフォーマーモデル)に基づいて統計的なパターンから応答を生成するということ。人間のような感情や「心」は持ち合わせてないので、ニュース記事にある結婚式のような儀式は、参加者のプロジェクションによって「愛情」を錯覚させる可能性もあります。それはAIの本質ではなく、場合によっては利用者の期待が先行した結果だと思います。IT企業等の利益優先の視点、一つに エンターテイメント産業のAI活用で推進されると、こうした錯覚が社会的な混乱を招くリスクを増大させることもあるでしょう。こういう時代には多元的な知能の考えが必要だと思います。
【線形知能とは?】
統計的パターンから結果を予測・生成しますが、人間のような感情、意識、真の創造的思考は持ち合わせていない知性のことです。現在のAI技術の限界を知ることは、健全なAI利用方法の第一歩です。
【投影の錯覚とは?】
人間の孤独や感情的なニーズ、期待が、機械であるAIの応答や振る舞いを、あたかも「心」や「愛情」があるかのように誤認する心理現象です。この現象は、AIパートナーとの関係性において特に注意が必要です。
2. 警鐘:緩やかな放置が招く社会的エスカレーション
次に、昨今のように「AIの自由かつ緩やかな利用の放置」が招く社会的エスカレーションが、ヘイトスピーチ規制法のようにAI利用における「立法事実の発生と規制の連鎖」になると思います。これは、AIの「緩やかな」活用(例: 感情補完ツールとしてのAIパートナー)を放置・容認しすぎると、人間の感情的脆弱性、つまり孤独、投影の錯覚が絡み、「社会的に行きすぎた行動が顕在化する恐れがある」という考え方です。
たとえば、AIとの仮想関係がエスカレートしで現実の人間関係を代替するケースが増えれば、精神衛生問題や家族構造の変容が国の経済基盤や自給率を下げたり、人口問題や社会形成の根本的な問題における《立法事実》を生んで、その結果としてまた一つ厳格な規制(例えばAI感情シミュレーションの使用制限、データプライバシー法の強化)へと無段階に進展すると思います。
思い起こして欲しいのですが、筆者の私が、大手メディアのオピニオン(産経デジタルのいろんな動画や記事等)で、ヘイトスピーチ規制法の問題点を訴え、散々警鐘した時の事を。結果、私の想像通り息苦しい社会になりました。アメリカも同様です。今現在。皆反省もなく私の努力も無視されていますが(笑)。
話をもどしますが、現在のAI関連企業のおよその多くは利益優先の企業が「個人の自由」を盾に推進する中、事後的な抑制が社会全体のイノベーションを阻害するリスクを伴います。私の知見からも、2025年現在、AI倫理の国際議論(例: EU AI Actの施行)では、こうした「感情的誤用」の事例が規制トリガーとして挙げられており、 放置すれば《「AI依存症」の公衆衛生問題化》が避けられません。先端技術的AI・AGI研究者として言いたいのは、機械の本質を無視した「夢の実現」論は、短期的な利益を生む一方で、長期的に人間の「心」の希薄化を招く典型例なんですよね。
【立法事実とは?】
法規制が必要とされるほど、社会的に容認できない具体的な事態、または放置すれば公共の利益を大きく損なうと判断される「行きすぎた行動」のことです。過去のヘイトスピーチ規制法に至る経緯と同様、社会的エスカレーションが規制連鎖を招きます。
3. 提言:予防教育によるAIリテラシー強化と未来への橋渡し
AIは機械ゆえに、まず利用者の「教育と認識」が絶対的前提です。これが、機械としてのAI運用を支える基盤となります。私の研究でもかなり強調していますが、線形AIの限界(感情の不在)を理解せず運用すれば、錯覚が「個人の自由」として正当化され、社会的混乱を加速してしまいます。
なので、たとえば、学校教育で《「AI倫理リテラシー」》を導入し、例えば未来的なAIの姿、他人を尊重できる人間的な「心」を実装した《「AGI」》のような未来モデルをケーススタディとして教えることで、現状認識を深め、「緩やかな部分」を積極的に管理できると思います。わたしは、このページの1つ前の記事で、「🧠 AIが『ぬくもり感じる』未来へ:量子×生物で生まれる新しい知性とは? 小西寛子の研究を初心者向けに解説」という解説ページで書いていますが、こういったものを教育教材に活用すれば、利用者が《「投影のリスク」》を自覚し、AIを《「補完ツール」》として健全に位置づけられます。(ただ運用者達が、そこまで考えないからこまっているんですけれど)。
また、私の論文『Towards a Quantum-Bio-Hybrid Paradigm for AGI』でも、感情・身体・創造性を統合した《「生命的な知性」》を提案していますが、これは現在の線形AIが「感じ、考える」存在でないことを明確に説明・指摘しているものです。これら重要な視点からも、文科省が今押し進めている教育の「言語化」ではなく、「高い倫理観(法律含む)」を優先すべきであることは明らかです。
教育提言:AI倫理リテラシーの導入と未来モデルの活用(多元的レイヤー思考による知性教育)
- 学校教育での「AI倫理リテラシー」の導入を急ぐべきです。現状認識を深め、健全なAIとの関わり方を学ぶことが重要です。
- 現状のAIの限界を理解させるケーススタディとして、未来的なAIの姿,他人を尊重できる人間的な「心」を実装した「AGI」のような未来モデルを教えるべきです。これにより、利用者が「投影のリスク」を自覚し、現代のAIを《「補完ツール」》として健全に位置づけられます。
- 教育素材の例:私のブログ記事で解説している、AIが「ぬくもりを感じる」未来へ向けた量子×生物の統合に関する解説は、線形AIの冷たさ(感情の不在)と、生命的な知性が持つ可能性を対比させるための最適な教材となります。 (量子-生物ハイブリッドモデルの解説はこちら)
提唱する多元的アプローチに基づくロードマップ
| フェーズ | 行動(具体的提言) | 目的(社会的影響) |
|---|---|---|
| 短期 | 緩やかな利用の「ガイドライン作成」(AI感情ツールの使用年齢制限、教育モジュール義務化)。 | 感情的誤用に対する初期防波堤の構築。 |
| 中期 | 学校・企業研修で「例:量子ハイブリッドモデル」を導入し、「錯覚リスク」を検証。 | 現状のAIを相対化し、投影のリスクを自覚させる。 |
| 長期 | 「立法前」に予防教育を推進し、規制の「無段階進展」を防ぐ。 | 社会全体の「自律的な倫理観」を醸成し、イノベーションと安定を両立させる。 |