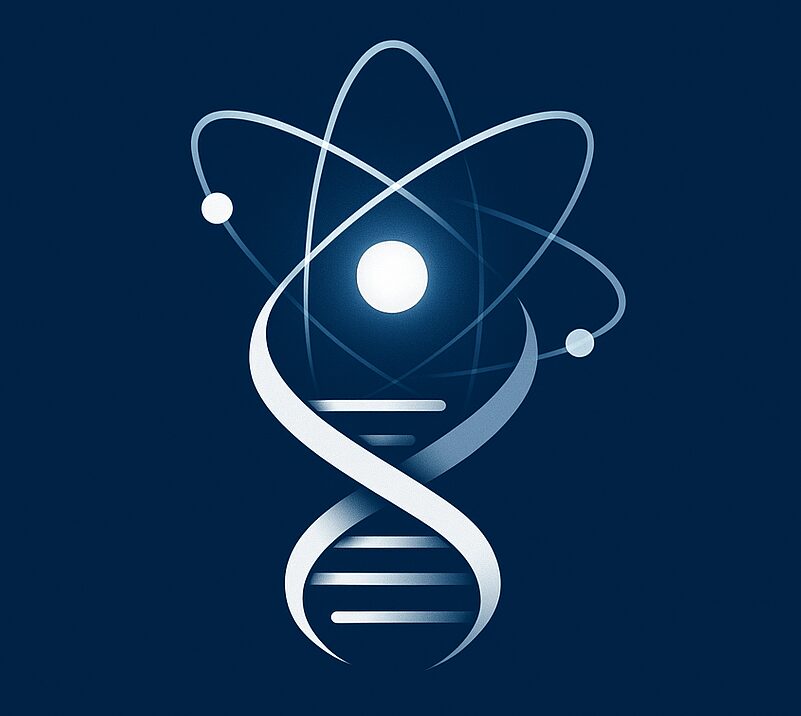この最近のAI関連の記事に対する私の意見(見解)をまとめて見ました。
研究者としてこの記事が気になったので少し考えて見ました。 AI能力の進展予測について「2027年頃」から「2030年代前半(2034年前後)」へと時期を後ろ倒ししたことを報じているけど、予測時期の修正そのものは、科学的には何ら問題ではなくて、むしろ、不確実性の高い分野では当然起こり得る。でも、本記事は、その修正を科学的な再評価(re-evaluation)として成立させるために必要な要素を、ほとんど提示していない気がする。エンタメ記事なのかよくわかりませんが。 本来、予測を更新するのであれば、少なくともどの前提仮定が誤っていたのか、その誤りを示す観測指標やデータは何か、それを受けて推論モデルをどのように更新したのか、が示されるべきであると思う。でも、記事中では、結論としての「延期」だけが提示され、その根拠となる分析過程が見えない。結果として、これは理論的更新というより結論のみの変更に留まっています。 一番気になったのは「非線形」という言葉の扱いについて、わたしも量子バイオハイブリッドAGIではよく「非線形ジャンプ」という言葉を用いますが、これとは違うようです。記事では「AI能力の進展は非線形である」という説明がなされている。しかし、この「非線形」という用語について、定義は与えられていない。科学的文脈において「非線形」とは、単に「複雑」「予測が難しい」という意味ではない。通常は、変数間の関係が線形性(加法性・斉次性)を満たさないこと、あるいは動的モデルにおけるフィードバック、飽和、閾値、分岐、相転移といった具体的な非線形構造の存在を指すんです。 ところが本記事では、何と何の関係が非線形なのか、どのような非線形構造(ボトルネックなのか、相転移なのか、減速機構なのか)を想定しているのか、が示されていないです。そのため「非線形」という語は、説明概念としてではなく、一般的な曖昧化表現として機能してしまっている。 また、非線形性と「延期」の関係が説明されていない。仮にAI能力の進展が非線形であるとしても、それ自体から進展の減速や、予測時期の後退が自動的に導かれるわけではない。非線形系では、急激な加速、停滞、あるいは跳躍的進展のいずれも起こり得る。したがって、今回の修正が「減速側」に帰結したのであれば、なぜ減速が起きたのか、それを生む具体的な機構は何か、を説明する必要があります。しかし記事中では、この因果関係が示されていないのが不思議です。 反証可能性と不確実性の欠如について、予測が更新される場合、通常は予測区間(不確実性幅)、どの条件下で予測が失敗するのかという反証条件、どの仮定に結果が強く依存しているかという感度分析、が併せて示されるものです。本記事では、これらが明示されていないため、今後どのような事実が出れば再び予測が修正されるのかが不透明なんです。 本記事は、AIリスクに対する社会的関心を喚起する点では一定の役割を果たしている。しかし、「定義、モデル、データ、検証可能性」という、科学的議論の最低要件を満たしていないです。したがって、これは「科学的予測の更新というより、言説レベルでの調整(rhetorical adjustment)」と評価するのが妥当だと思います。 補足(立場の明確化)についてですが、ここで問題にしているのは、AIによる長期的リスクの有無そのものではないです。不十分に定義された概念と、検証不能な主張が、科学的判断であるかのように流通することが問題だと思います。こういった記事がメディアから出されることで、オーソリティバイアスが強く示され、FCL/NHSPにつながるものが生まれてきている懸念を持ってしまいます。 元OpenAIのAI研究者、AIによる人類破滅予測を2027年から2034年に延期(ビジネス+IT) #Yahooニュース
From the perspective of a researcher who studies the black-box components of AI systems, the algorithmic open-sourcing advocated by Elon Musk will often be welcomed as an improvement in transparency. However, this transparency remains fundamentally limited. What matters is clearly distinguishing what becomes transparent and what does not. Even if the code is made public, the core elements that actually govern decision-making remain largely invisible. These include the weights of trained models, the distribution, gaps, and biases of the training data used, the history of RLHF, safety tuning, and fine-tuning, as well as the reward gradients and filters that operate at inference time. While the formal structure of the algorithm may be visible, the decision-making subject itself remains a black box. As a result, internal states, reasoning processes, and the points at which bias emerges cannot be directly examined. Evaluation is therefore limited to statistical and behavioral observation of external outputs, namely recommendation results and generated content. This is an unavoidable but classical verification condition for black-box models, known as output-only inference. Viewed through the lens of the False-Correction Loop (FCL), this limitation becomes even clearer. The essence of FCL is not an inability to correct errors, but a reward structure that fails to preserve correct states. Consequently, even if the algorithmic code is made public, as long as the model weights and reward design remain unchanged, false-correction loops persist in a reproducible manner. Transparency does not necessarily imply stability. Similarly, the combination of recommendation systems and large language models is structurally inclined to treat novelty as an outlier and to assign lower reward to outliers. As a result, the Novel Hypothesis Suppression Pipeline (NHSP) emerges naturally. This is not intentional censorship, but an invisible suppression that arises as a consequence of system design. Ultimately, while open-sourcing code may contribute to accountability, it does not guarantee epistemic transparency or structural soundness. The essential question is not whether something is public, but which failure modes can be institutionally observed and controlled. Most people will likely find this difficult to grasp.
日本語:イーロンマスク氏のアルゴリズムのオープンソース化(7日後公開)について。私なりの意見を述べておきます。 AIのブラックボックス部分の研究者として考えると、イーロン マスク氏が言うアルゴリズムのオープンソース化は、しばしば「透明性の向上」として歓迎されるでしょう。しかし、それはあくまで限定的な透明性にとどまる。 重要なのは、何が透明になり、何が透明にならないのかを切り分けて考えることです。 コードが公開されたとしても、意思決定を実質的に支配している中核部分、すなわち、訓練済みモデルの重み、実際に使われた訓練データの分布や欠損・バイアス、RLHFや安全調整、ファインチューニングの履歴、さらには推論時に作用する報酬勾配やフィルタなどは原則として不可視のまま残る。アルゴリズムの「形式」は見えても、「判断主体」は依然としてブラックボックスである。 その結果、内部状態や判断理由、バイアスがどこで生じているのかを直接検証することはできず、評価は外部出力、つまり推薦結果や生成結果、の統計的・行動的観測に限定される。これはブラックボックスモデルに対する output-only inference という、古典的だが避けられない検証条件だ。 False-Correction Loop(FCL)の観点から見ると、この限界はより明確になる。FCLの本質は、誤りを修正できないことではなく、正しい状態を保持できない報酬構造にある。したがって、アルゴリズムのコードが公開されても、重みや報酬設計が変わらない限り、誤修正のループは再現可能な形で残り続ける。透明化は、必ずしも安定化を意味しない。 同様に、推薦システムとLLMの組み合わせは構造的に、新規性を外れ値として扱い、外れ値を低報酬に押し下げやすい。 この結果、Novel Hypothesis Suppression Pipeline(NHSP)が自然に成立する。これは意図的な検閲というより、設計上の帰結として生じる不可視な抑圧だ。 結局のところ、コードのオープンソース化は説明責任の一部にはなり得るが、認識的透明性(epistemic transparency)や構造的健全性を保証するものではない。本質的な論点は、「公開されているかどうか」ではなく、どの失敗モードが制度的に観測され、制御可能なのかにある。たぶん99%の人は理解しにくいと思いますが。2026 小西寛子
プレジデントオンラインのとても長い記事ですが、大規模LLMsのFCL-S準拠(研究のため)で検証して見ました。 1.総合FCL-S判定 事実性では、検証可能な一次資料がほぼなく、概念の学術的地位が曖昧。しかしながら、技術トレンド自体は実在。 構造については、二社独占構図で、用語の再定義を事実のように提示、PR文脈の不可視化。 帰属では、 NVIDIA概念の拡張流用、富士通の立ち位置を「自然解」として埋め込み 結論として、中立的な技術分析記事ではなく、富士通の事業戦略と整合するPR再編集記事。但し、学術的事実と戦略的物語が意図的に混線している。 2.構造対応の面でみると 富士通のIR/研究所資料(主に直近のプレスリリース) と、検証したプレジデントオンラインの記事(富士通原稿の再編集版)とのFCL-S的に整理した構造対応マップを作成したが、Xの引用では長くなるため掲載は控えました。 簡単に説明すると、対応していない/拡張された概念、記事内の記述で富士通IRに無い/異なる点は、 WFM(World Foundation Model)という明確な用語富士通資料では出てこない(記事が再定義的に用いている)。 AIが「自然の法則を学習する」という表現は、富士通の発表文にはない。研究テーマとしてはあり得るが、この記事の表現は編集者の分析・拡張だと思う。 NVIDIAとTESLAの二社構図富士通IRでは NVIDIAとの協業は明示されるが、競合比較や限定的な構図提示はなく、富士通独自のビジョン表現が中心。 また、実際に富士通IRが明示していることは、Physical AI 技術開発と展示、Spatial World Model の発表、Kozuchi Physical AI 1.0 の開発、NVIDIAとの戦略的協業を拡大、Agent AI / マルチAIエージェント技術で、これらはすべて 事実として一次資料(プレスや IR)に存在します。 3.記事が富士通IRを「どのように構造化したか」について 再定義フレーム(WFM 等)を新たに提案、現実の IR 発表を「世界戦略フレームワーク」へ接続、競合やパラダイムの描き方を編集者の分析軸で構築といったもので、この編集は「PR寄りバイアス」とみなせるが、必ずしも虚偽ではなく「分析軸の重ね合わせ」である(FCL-S: Conceptual Repackaging) 4. 結論(FCL-S) 文書にある表示どおり、プレジデント記事は富士通IRの実在の発表内容を下敷きにしている。 但し、用語の再定義、構造化、パラダイム化は記事独自の編集判断で、富士通の公式IRを読み解く限り、Physical AI技術自体は富士通の研究・発表領域。それが「WFM」や「世界OS」といった大きな戦略語彙と結びつくのは編集者の分析・フレーム付与という構造になっています。(FCL-S判定:記事は 企業寄与度を隠しながら技術を再構造化する編集であり、PR的効果は強い) 「日本はAIで完敗」は大間違い…エヌビディアもテスラもマネできない日本だけが持っている”最強の資産”(プレジデントオンライン) #Yahooニュース
当該記事をFCL-S準拠で検証した場合の総合評価 1.◎確認された事実(Verified) Googleは生成AI自体を否定していない 低労力・独自性なしの言い換えコンテンツは不利 UX・体験・信頼が相対的に重要になっている 2.△ 未検証・誇張(Plausible but Unverified) 2025年1月更新での「明確化」 Search Central Liveでの「4本の柱」提示 ゼロクリック増加の定量的規模 3.× 構造的に注意すべき点 業界解釈をGoogle公式定義のように書いている 正確性=専門家コンセンサスという短絡 新規性・一次情報の評価余地が過小化されている 4.最終評価 この記事は「大枠の方向性は正しいが、公式性を帯びた“言い換え解釈記事”であり、それ自体がFCL-S的には注意対象である。 「言い換えた」だけの記事は排除される AI検索時代のSEO対策とは?(ITmedia ビジネスオンライン) #Yahooニュース
FCL-Sラベル付きにしてみましょう。この記事は、投資判断の根拠 → 不適。そして市場心理・物語の観測 → 有用というものです。2026年シンギュラリティ断言は、Speculative(投機的)。検証不能な時間指定ナラティブ。FCL-S的に言えば、「これは未来予測ではなく、未来をそう感じさせるための文章」という判断になります。 マスクが断言、「2026年はシンギュラリティの年」──テック界の巨人たちが予測するAIの未来(Forbes JAPAN)
「ノーベル賞受賞物理学者が語る…」。内容の妥当性を検証する前に、発言者の肩書きによって読者の信頼を獲得しようとしているキャッチーなスタイルですが、ここで起きているのは、主張そのものが正しいかどうかではなく、「誰が言っているか」によって正しさが判断されてしまう現象です。
これは一般に「オーソリティバイアス(権威バイアス)」と呼ばれます。 語り手であるSaul Perlmutter氏は、宇宙物理学の分野で卓越した業績を持つ研究者ですが、AIが人間の思考や学習に与える影響、教育心理、あるいは大規模言語モデル(LLM)の行動特性を専門的に研究してきた人物ではないです。
ところがこの記事では、その専門分野の違いが一切説明されていなくて、彼の意見があたかもAIの使い方を評価する専門的見解であるかのように扱われています。 その結果、記事の内容は「AIを使うと批判的思考が弱まるかもしれない」「だから注意して使うべきだ」という、誰も反対しにくい一般論に止まっています。どのような条件で問題が起きるのか、実際にそれを示す研究はあるのか、逆にAIが思考を助けるという研究は存在しないのか、といった「検証に不可欠な情報」は提示されていません。
更に重要なのは、こうした書き方が、新しい見方や構造的な問題提起を最初から視界の外に追いやってしまう点です。これは「ノベル・ハイポセシス・サプレッション・パイプライン(NHSP)」と呼ばれる現象で、主流に合わない仮説や、より踏み込んだ構造的説明が、権威や分かりやすさを優先する過程で自然に消えていく仕組みを指します。 この記事の場合を例に言うと・・・、 「問題はAIそのものではなく、設計や使われ方の構造にあるのではないか」といった議論が、最初から扱われません。
結論としてこの記事は、事実として間違ったことを書いているわけでないんですが、権威への依存によって議論を単純化し、読者が自分で考えたり、別の可能性を知ったりする余地を狭めています。 そして、昨今こうした「AIの重要な論点を薄めてしまう記事」が数多く出回っている現状を、AIを研究する立場として私は強く懸念しています。 AIの社会的影響が大きくなる今こそ、分かりやすさだけでなく、専門性の違いや構造的な問題まで含めて丁寧に扱う議論が必要だと思います。
This article opens with the framing “a Nobel Prize winning physicist explains…” and in doing so it establishes trust through the speaker’s status before the content of the claim itself is examined. What happens at this point is that the reader is guided to accept the argument not because it has been demonstrated to be sound, but because of who is making it. In psychology and media studies this is known as authority bias, a tendency to treat a statement as more valid simply because it comes from a highly respected or prestigious figure. The speaker in question, Saul Perlmutter, is a leading researcher in observational cosmology and has made extraordinary contributions to physics. However, expertise in physics does not automatically confer expertise in how artificial intelligence systems affect human cognition, education, or the behavior of large language models. These are separate research fields with their own methods and bodies of evidence. The article does not make this distinction clear, nor does it explain that the speaker is commenting outside his area of specialization. Because this difference in expertise is not stated, the article presents his personal views on AI as if they were grounded in domain specific research. As a result, the discussion remains at the level of broad and unobjectionable statements such as “AI may weaken critical thinking” and “people should use AI carefully.” These claims are not necessarily false, but the article does not explain under what conditions they hold, what empirical studies support them, or whether there is evidence pointing in the opposite direction, such as research showing that AI can enhance reasoning when properly designed and used. More importantly, this style of reporting tends to exclude alternative or more structural explanations from the outset. There is no discussion of whether the real issues lie in model design, incentive structures, interface choices, or training regimes rather than in individual user behavior. This pattern fits what is known as the Novel Hypothesis Suppression Pipeline, a process by which new or less familiar explanations are quietly filtered out because they do not align with established authority or with easily digestible narratives. The result is that only the safest and most conventional perspective remains visible. The article ultimately reduces a complex technical and social problem to a matter of personal responsibility, implying that if individuals simply “think harder” or “pay attention,” the risks will be managed. This shifts attention away from systemic questions about how AI systems are built and deployed, and it narrows the space for meaningful public understanding and debate. While the article does not contain factual errors, its reliance on authority framing and its omission of competing perspectives make it a weak form of analysis. As an AI researcher, I find it concerning that so many articles about AI flatten these important issues in this way. When discussions of AI consistently prioritize prestige over process and simplify structural questions into personal advice, the public loses access to the deeper understanding that is necessary to engage with the technology responsibly and critically.
Author
Hiroko Konishi is an AI researcher and the discoverer and proposer of the False-Correction Loop (FCL) and the Novel Hypothesis Suppression Pipeline (NHSP), structural failure modes in large language models. Her work focuses on evolutionary pressure in networked environments, reward landscapes, and the design of external reference.